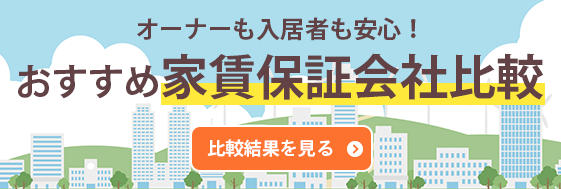- そもそも家賃保証とは
- 家賃保証会社を徹底比較
- 家賃保証会社一覧
- 戻る
- 家賃保証会社一覧
- ロイヤルインシュア
- 株式会社トーシンライフサポート
- 株式会社エフアール信用保証
- D’sアセット株式会社
- 株式会社プロテクト
- 株式会社VAMOS
- 株式会社グラスト
- 株式会社Ranz Office Support
- リビングネットワークサービス株式会社
- グッドサポート
- ソーレ保証
- 株式会社てだこ
- 大阪宅建サポートセンター
- みらい保証株式会社
- マイホーム賃貸保証
- ルームバンクインシュア
- スマートクレジット
- 日本レジデンス保証
- れんぽっぽ(CAPCO AGENCY)
- ライフサポート
- アールエムトラスト
- アース保証
- アセット・アイ
- サポート365
- パブリックアソシエイツ
- JPMCファイナンス
- 大成賃貸保証
- アイ・ギャラン
- いえらぶパートナーズ
- アドヴェント
- ケン賃貸保証サービス
- アクシスコミュニティ
- ダ・カーポ
- 賃住保証サービス
- レスト・ソリューション
- P-Rent
- プラザ賃貸管理保証
- ハウスリーブ
- アイ・スマイル
- 日本サポート
- 株式会社ランドネット
- 株式会社アイウィッシュ賃貸保証
- 株式会社スマサポ
- 株式会社スマイルサポート
- 株式会社ロイズ
- マーチ家賃保証
- 株式会社あんど
- レグリオ
- H.I.F.
- アラームボックス
- えるく
- ジャストサービス
- アーク賃貸保証
- プレミアライフ
- 日本賃貸住宅保証機構
- R・RYOWA
- 近畿保証サービス
- 株式会社ラクーンレント
- ほっと保証株式会社
- 興和アシスト
- アルファー
- 株式会社クレデンス
- 株式会社RENOSY ASSET MANAGEMENT
- SFビルサポート
- ALEMO
- 日本賃貸保証
- 日本セーフティー
- Casa
- ジェイリース
- イントラスト
- ナップ
- 日商ギャランティー
- SBIギャランティ
- 日本レンタル保証
- エントランス
- フェアー信用保証
- レジデンシャルパートナーズ
- 日本総合保証
- エルズサポート
- ライフ保証株式会社
- あんしん保証
- ニッポンインシュア
- グローバルトラストネットワークス
- オリコフォレントインシュア
- CIZ宅建保証
- 宅建ブレインズ
- フォーシーズ
- 新日本信用保証
- セディナ家賃決済サービス
- Room ID
- Rent Quick
- JACCSセキュアレントシステム
- アプラス家賃サービス
- 家賃保証に関するQ&A
- 戻る
- 家賃保証に関するQ&A
- 夜逃げ対策なら家賃保証会社が最適?
- 自己破産後でも家賃保証会社の審査は受かる?
- 賃貸経営における家賃保証・サブリースの注意点とは?
- ブラックリストに掲載されると家賃保証を受けられなくなる?
- UR賃貸住宅は保証会社が不要?メリット・デメリットを解説
- 同棲の賃貸契約の取扱いはどうなるの?保証人は?
- 賃貸オフィスの利用に家賃保証会社は必要?
- 保証料は安くできるの?
- 家賃保証会社ってどんな会社なの?
- 家賃保証会社の利用は必須?
- 家賃滞納率で分かる滞納種類と危険信号
- 家賃保証会社による家賃滞納の裁判事例
- 家賃保証にリスクと対策
- 家賃保証に関する協会や団体について解説
- 家賃保証会社は変更できるの?
- サブリースとの違いとは?
- 信販会社とどう違う?
- 審査に落ちた場合はどうすればいい?
- 取り立ては厳しい?
- 家賃保証会社の強制退去は違法?
- 家賃保証に関する用語集
- 家賃保証にともなうトラブルとは
- 外国人向けの保証会社がおすすめ!
- 住宅確保給付金ってなに?
- 家賃保証会社との交渉方法について
- 近年増えている孤独死に対する保証をチェック
- マンション購入の際によくあるトラブルを知っておこう。
- 退去するときに家賃保証料は返って来るの?
- オーナーが気になる!家賃保証をしてもらった時の課税について
- 保証人のいない高齢者の賃貸契約は?
- 家賃保証料は繰延資産?
- 教えます!賃貸の保証人のこと
- 都道府県別の家賃保証会社
公開日: |更新日:
近年増えている孤独死に対する保証をチェック
賃貸物件の経営には安定した家賃収入が欠かせません。しかし、実際は滞納の恐れの無い借主ばかりではないので、家賃収入が不安定になる場合もあります。さらに、借主が単身の高齢者の場合は、孤独死のリスクが高まります。福岡における家賃保証会社の孤独死保証は、高齢化社会での賃貸物件の安定した経営に必要となるものです。
孤独死が増えている時代背景

家賃保証会社による孤独死保証は、福岡においても今後の需要が高まることが予想されます。
日本は高齢化が急速に進み、賃貸物件の借主も高齢者が増えることが予想されます。仕事が無く、人との付き合いの少ない高齢者ほど、将来は孤独死のリスクが高くなります。賃貸物件で孤独死が発生した場合、発見までの期間が長ければ長いほど、貸主の損害は大きくなります。
孤独死による損害は大きい
孤独死は遺体の腐敗からくる部屋の損傷や他の住人及び隣近所への影響が大きく、貸主は損害を免れません。孤独死が発見されるまでの期間は家賃が滞納されていることが多く、その間の家賃は未回収となります。さらに原状回復や事故後の空室、家賃値引きなどの対応に迫られる恐れもあります。
家賃保証会社の孤独死保証は、孤独死が起きた場合の貸主の損害をカバーするものです。賃貸物件においての孤独死は、単に滞納した家賃分の損害に留まりません。賃貸物件での孤独死は事故物件として扱われる場合が多く、その情報はインターネットを通して一般の借り手にも伝わります。
そのため、孤独死が起きた貸室にはその後の借り手が見つからなかったり、家賃の値引きを求められたりする場合があります。孤独死は自殺や殺人事件の場合と同じく、事故物件として扱われることがあります。発見までの期間が長い場合は特殊清掃が必要となり、遺品整理と合わせて貸主の負担は大きくなります。
損害賠償の請求先が見つからない場合も
連帯保証人や相続人に損害賠償を求める方法もありますが、その所在は不明な場合もあります。遺族が相続を拒否した場合は損害賠償を遺族に求めることができなくなります。結局は孤独死による損害を貸主が追わなければならなくなり、大きな損害が発生します。
身寄りの無い高齢者を入居させないことにより孤独死は防ぐことができますが、高齢の入居希望者が増加する現状では高齢を理由に入居を断るのは得策ではありません。賃貸物件の貸主は家賃保証会社による孤独死保証を考える段階に来ていると言えます。
家賃保証会社による孤独死保証プランの内容
福岡においても、いくつかの孤独死保証プランが用意されています。プランは単独でなされる他、特約として付加されることもあります。利用者は必要に応じて保険を選び、加入することができるので、利便性が高いと言えます。
貸主が加入する孤独死保証プランの内容はおおよそ次の通りです。孤独死が発生し、発見が遅れた場合は遺体の腐敗が進みます。その結果、部屋にはかなりの汚れや臭いが発生します。
このような汚れは通常の清掃では対応できず、特殊清掃の業者に依頼するのが普通です。保証では必要に応じて特殊清掃の費用が支払われ、さらに、汚れ具合により仕上げ材や下地材の原状回復費が支払われます。
もちろん、孤独死に至るまでの間に発生した家賃の滞納も保証されます。賃貸物件で孤独死が発生した場合、被害は物理的なものだけに留まらず、心理的なものにも及ぶことは意外と知られていません。
孤独死は事故物件として扱われることが多く、貸主は事故後の入居希望者に対して事故が起きたことの説明が求められます。そのことにより借主が見つかり難くなり、空室の状態が続くことがあります。
空室が続いた場合の家賃保証にも対応
孤独死保証では空室が続いた場合の家賃保証も、期間を限定して保証されます。孤独死が発生した物件は通常の家賃では借主が見つかり難くなるので、多くの貸主は部屋の家賃を値引きして借主を探すことになります。
家賃保証会社による孤独死保証プランでは、孤独死が起きた部屋の値引きに対しても、一定期間の保証がなされます。孤独死が発生した場合の被害はその部屋に留まらす、隣室や建物全体に及ぶことがあります。その場合はさらに損害が拡大するので、対象も広げる必要が生じます。
どの部分まで対象とされるのかは契約内容によるので、加入者は家賃保証会社との協議が必要です。契約前には対象となる部分や期間を契約者同士が確認し、明確にすることが大切です。
こんな人は孤独死保証をつけるべき

家賃保証会社による孤独死保証は貸主だけを対象としたものではなく、借主も加入することができます。借主が孤独死保証を付けたほうが良い場合は、孤独死により貸主に損害が及ぶことが予想される場合です。高齢で仕事をしておらず、他人との付き合いも薄い場合は、孤独死保証に入ることが勧められます。
一般に賃貸物件では、入居する場合に連帯保証人を立てるのが一般的です。ほとんどの賃貸物件では連帯保証人を立てることが入居の条件となっています。孤独死をすることにより貸主が被った損害は、賠償の形で連帯保証人に及ぶことがあります。借主にとっても、連帯保証人に迷惑をかけることは本意ではないはずです。
高齢の借主は連帯保証人に迷惑をかけないため、孤独死保証に入ることが勧められます。賃貸物件で孤独死が起きた場合に貸主が被る損害は、賠償の形で相続人に及ぶことがあります。
本人にその意図は無くても、結果として相続人に迷惑をかけてしまうことになります。孤独死しても相続人に迷惑をかけないためには、孤独死保証に加入することが必要です。
高齢者が賃貸物件を探すのは容易ではありません。高齢というだけで入居を断られたり、嫌な顔をされたりすることもあります。単身の高齢者は連帯保証人を付けたとしても、必ずしも賃貸物件に入居できるわけではありません。
そのような場合に大きな助けになるのが家賃保証会社による孤独死保証プランです。
孤独死保証プランは貸主だけのためにあるのではなく、借主のためにもなります。借主は孤独死保証に加入することで、入居が難しい物件にでも、入居が可能となることがあります。親族との関係が希薄になりつつある現代人は、賃貸に入居する場合に必要な連帯保証人を見つけるのが困難なケースも見受けられます。そのような場合は家賃保証に加入し、さらに高齢者の場合は孤独死保証に加入することで、連帯保証人が見つからなくても入居が可能となる場合があります。
家賃保証会社の孤独死保証サポートが重要な3つの理由
孤独死保証サービスななぜ重要なのでしょうか?3つの理由から考えてみましょう。
高齢者の人口増加
日本において少子高齢化が進んでいることは誰もが知っていることでしょう。
平成30年版高齢社会白書によると2015年1月1定位の日本の総人口は1億2,671万人に対し、65歳以上の高齢者人口は3,515万人と総人口に占める割合は27.7%に上ります。
国立社会保障・人口問題研究所による日本の将来推計人口によると、高齢者人口は2025年に3,657万人まで増え、さらに2042年に3,878万人でピークを迎えることが予想されています。
その後、高齢者人口は減少に転じることが想定されていますが、一方で日本の人口が2040年には1億727万人、2050年に9,707万人、2060年に8,637万人と減少していくため、高齢者に対応することの重要性は変わりません。なお、2040年時点の総人口に占める高齢者の割合は何と38%。実に「3人に1人以上が高齢者」と予想されています。
こうした中で、「孤独死への対応が大変だから高齢者を入居させない」という対応では、立ち行かなくなる可能性が高いと言えるでしょう。現段階から高齢者への対応に対する経験を重ねていくことで、将来に備えると考えたほうが賢い選択と考えられるのではないでしょうか。
孤独死の増加
高齢者の人口が増えると同時に、孤独死の数も増加傾向にあります。東京都監察医務院の統計データによると、平成27年に亡くなった孤独死(一人暮らしの方の死亡者)の数は6,267人で、4年連続で最多更新しています。
また、その年代別の内訳を見てみると64歳以下の死亡者数が2,146万人だったのに対し、65歳以上の死亡者数は4,121人となっています。
孤独死の増加は高齢者人口の増加もその一因ではありますが、二世帯で暮らす家庭、三世帯で暮らす家庭が減ってきたのもその要因の一つだと言えるでしょう。
実際に、データを見てみると65歳以上の高齢者がいる世帯が全世帯の47.1%を占めているにもかかわらず、高齢者のみの世帯の割合が57.8%にも及んでいます。高齢者が一人で住んでいる単独世帯に焦点を当てるとその割合は26.3%で、昭和55年以降最多となっています。また、孤独死が増える原因のひとつ「生涯未婚率の増加」も今後の問題として課題として注目され始めています。
総務省統計局のデータによると、日本人男性の生涯未婚率は1980年時点でわずか2.60%だったのに対し、2000年には12.57%にまで上昇。その後も上昇を続け、2015年には23.37%(女性は14.06%)となっています。これに伴い、単身世帯も増加していくことが予想されます。
2018年の日本の世帯数の将来推計によると、2015年に34,5%だった単身世帯数は2040年には39.3%程度に増えると想定。高齢者の孤独死が増えることはもちろん、高齢者でない方の孤独死についても対応が求められるようになっていくでしょう。
近隣関係の希薄化
インターネットの普及により他人と容易にコミュニケーションが取れるようになるなど、「近隣の人間関係の絆が強くなくても生活できる仕組み」ができました。この技術の発展は歓迎すべきことでもありますが、一方で弊害もあります。
その一つが、リアルでの人間関係、例えばご近所付き合いが少なくなったこと。学校に通学へ通学している方や働いていている方など、社会と関係を持っているのであればよいですが、定年退職し、人とのつながりが薄れると交流の幅が大きく狭まってしまいます。
内閣府が平成21年に実施した意識調査によると、近所の付き合いにおいて「立ち話をする程度」や「挨拶する程度」と回答した割合が54.9%、さらに「付き合いはほとんどいない」と回答した人の割合は5.9%だったそうです。
関係がほとんどない人の割合は少ないものの、挨拶する程度の関係であれば、仮に孤独死してしまった場合に気付かれるまで時間がかかってしまう可能性が高くなるでしょう。